- 「挟殺プレーが上手くいかない」
- 「アウトにするのに時間がかかってしまう」
このような悩みを抱えている選手や指導者の方に向けて、今回は挟殺プレーについて解説します。
挟まれるランナーは本来アウトになるランナーであり、ミスしてアウトにできないと心理的なダメージが大きいため、挟殺プレーは重要度の高いプレーです。
また、プロでも失敗してしまうプレーであり、時間がかかるとほかのランナーが進塁してしまうため、難易度の高いプレーでもあります。
しかし、挟殺プレーはランナーとの距離を詰めるタイミングを知る、チームでルールを徹底することで確実に処理できるプレーです。そこでこの記事では、挟殺プレーの基本ルールや意識すること、練習方法を紹介します。
また、この記事は筆者の経験や知識をもとに解説していますが、すべてを実践する必要はありません。一部でも実践できるものがあり、少しでも参考になれば幸いです。
挟殺プレー 距離を詰めるタイミング

そもそも挟殺プレーのなかで、最もランナーとの距離を詰めれるタイミングはどこでしょうか。それは、ランナーが切り返すとき(受け手が捕球するとき)です。
まずはこちらの動画をご覧ください。

動画を見てわかるように守備側は前に出ながら捕球するため加速しやすいですが、ランナーは止まって逆方向に走るため加速しづらいです。この加速の差を利用してランナーとの距離を詰めます。
挟殺プレー 基本ルール

次に挟殺プレーの基本ルールとその必要性を紹介します。基本ルールは以下の5つになります。
- 本塁から遠い塁に追い込む
- 受け手は前に出ながら捕球する
- 受け手の合図で投げる
- 追うときボールは利き手に持ち替える(グローブで持たない)
- 追うときは利き手側にずれる
1つ目の本塁から遠い塁に追い込むのは、挟殺プレーでミスしても進塁はさせないためです。前の動画では2・3塁間で挟殺プレーを行っていますが、投手がゴロを捕球して3塁側から回り込み2塁に追い込むように追っています。そのため、受け手が合図を出すタイミングは、本塁に近い側は気持ち早めに合図を出すようにします。
2つ目の受け手は前に出ながら捕球するのは、ランナーとの距離を詰めるためです。先述しましたが、ランナーとの距離を最も詰めれるのはランナーが切り返すとき(受け手が捕球するとき)です。そのため、受け手が前に出ながら捕球するのは徹底するべきです。
3つ目の受け手の合図で投げるのは、受け手がしっかりと前に出ながら捕球するためです。投げ手のタイミングだと、受け手はいつ投げられるかわからないため前に出られませんが、受け手がタイミングを決めることで勢い良く前に出て捕球できます。
ちなみに偽投(投げるふり)ですが、挟殺プレーではやらない方が良いと筆者は考えます。偽投はランナーをひっかけられますが、受け手も前に出にくくなってしまいます。繰り返しになりますが、ランナーとの距離を詰めるために重要なのは受け手です。そのため、これらのルールは重要になります。
4つ目の追うときボールは利き手に持ち替えるのは、受け手の合図ですぐに投げられるようにするためです。ボールがグローブに入ったまま追っていると、受け手に合図を出されてもすぐに投げられません。目の前にランナーがいる場合はグローブにボールが入った状態でタッチした方が良いですが、追いつけるか微妙な距離の場合は利き手に持ち替えて追った方が良いでしょう。
5つ目の追うときは利き手側にずれるのは、送球がランナーに当たらないようにするためです。投げ手、ランナー、受け手が一直線に並んでいると当然ランナーと被ってしまいます。送球がランナーに当たらなくても、ボールの出どころが見えないと受け手は捕球しづらくなってしまうので、ボールの出どころが見えやすいように投げ手が利き手側にずれると良いです。
挟殺プレー 注意するべきこと

次に挟殺プレーで注意すべきことを紹介します。それは何かというと、スリーフィートオーバーの対応です。
スリーフィートオーバーとは簡単に説明すると、ランナーが守備のタッチを避けるために走路から3フィート以上離れてアウトになることです。
こちらの動画がわかりやすいです。

ではスリーフィートオーバーをどのように判断するかというと、野手が手を伸ばしてもタッチできないほど走路から外れているかどうかです。言い換えると、野手が手を伸ばさない(タッチしようとしない)とスリーフィートオーバーを取られないことが多いです。
そのため、ランナーが走路から外れているときもスリーフィートオーバーだと決めつけるのではなく、必ずタッチしに行くようにしましょう。
挟殺プレー まとめ
今回の内容をまとめると以下のようになります。
- ランナーと距離を詰めるのは、受け手が捕球するとき
- 挟殺プレーの基本ルールは5つ
- 受け手は前に出ながら捕球する
- スリーフィートオーバーでもタッチしに行く
挟まれるランナーは本来アウトになるランナーであり、ミスしてアウトにできないと心理的なダメージが大きいため、挟殺プレーは重要度の高いプレーです。
また、挟殺プレーは基礎的な技術が詰まったプレーですので、指導者の指導力の見せどころです。
こちらの記事では内野守備の指導法を紹介しています。興味がある方は是非ご一読ください。



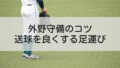
コメント